日本陸軍 第二師団 歩兵第十六連隊 新発田 あやめ会 戦記 戦死者名簿 ガダルカナル 雲南 ビルマ ジャワ ノモンハン 遺骨収集 政府派遣
生と死の極限に生きて
イラワジ河畔の大会戦

十六連隊激戦の地(イラワジ河---タリンゴン附近)
ここは既にイラワジ河畔に近く戦場である。
銃砲弾は飛んでこないものの、砲声が雷鳴のように聞こえてくる。
一月十六日夜、連隊本部要員として補充になった同集落の長谷川二郎君(私より二学年上級)が私の幕舎に、「准尉殿、もしも私が戦死したらこれを家に届けていただきたい」と言って印鑑、肉池、婚約者の写真を持って来た。
私は、長谷川君、俺だって明日の戦闘で死ぬかもしれない、と言ったが、結局それを受け取って後方行李班にいる横山○(言べんに忠で一文字)君に持っているように届けた。
この長谷川君はタリンゴン攻撃の際、連隊本部がマンゴ林に布陣していたとき、猛烈な敵の砲撃をうけた。
初めて戦場に出た者の悲しさ、砲弾が落ちる度に移動するので、遂に砲弾によって即死した。
絶対に砲弾は同じところへ落ちないのだから、一発目が当たらなかったら、そこを動かなければよいのだ。
私は衛生兵から鋏を借りて、長谷川君の親指を切って包帯に包んで遺品と一緒に、これも横山君に託した。
これは最後まで持って帰り、ご遺族に渡した。
余談になるが切った指が腐って臭くてどうしようもないと横山君が持って来たので、肉を全部落として骨だけにして包んだ。
南方作戦においては六千名近い戦死者があったが、遺骨を処置する余裕がなかったために日本へ送還出来なかった。
誠に残念なことであった。
イラワジ河は堤防も無く、自然流下して雄大なビルマを横断する川である。
その河畔の地形も平坦地で、点在する集落の他は遮るものもなく、一望千里の平原である。
このような地形において、制空権と火砲の劣勢な状況での戦闘は不利そのものであった。
越路春海氏著の『ビルマ最前線』四十二頁に第二師団のことについて、次のように書いてある。
「当時、『森』方面軍(勇という防諜名を昭和十八年三月十七日ビルマ方面軍司令官、河辺正三中将によって編成されてから『森』と呼称された)では増加兵力を要請し続けていたが、ようやく昭和十九年一月になって第二師団『勇』と第五十三師団『安』が増加された。
『勇』は仙台の常備師団(大東亜戦争にあっては随時混成兵団が編成され、常備師団とは明治以来常備されたことを意味する)でガダルカナル島からの撤退部隊だ。
フィリピンで再建して、師団長は岡崎清三郎中将。
ガ島生き残りが中核となっていたが、あわれ再び惨劇のルツボに投入されて、さすがの東北健児たちも『ビルマ』は『ガ』島どころのもんじゃねェスと目を白黒することになる。」
事実戦死者においても十六連隊は、断作戦とイラワジ河大会戦を合わせてガダルカナル島と匹敵するものとなった。
ガダルカナル島の戦死者との違いは餓死や栄養失調ではなく、近代科学兵器による犠牲者である。
戦死者が多くなった理由のもう一つは平坦地における戦場の地形条件であろう。
雲南作戦にあっての中国軍は北支事変と違って、日本の学徒動員に等しい青少年であり、愛国、救国精神の旺盛な兵器の質の違いがあった。
イラワジ河畔にあって敵は南北千百キロに及ぶ広範な戦場を電探、空中射撃戦術、これを駆使して円筒形攻撃戦術等すべて我々の持つ戦力とは桁違いの戦力に対しての戦いであった。
長い鎖国の夢から覚めて目をこすりながら三八式歩兵銃の先に剣をつけて意気込んだ大和魂のみでは通用しなかった。

優秀な医学者として召集従軍された佐藤善達軍医
今は逝き新潟市出身の佐藤善達軍医少尉は当時、こんなことを仰った。
「どうにも先の見えない、作戦上理にも叶っていない、こんな戦争で死にたくない、私は科学者として未だ研究をし、やらねばならないことがあるのだ。あんたも命を大事にしなさい。」
佐藤氏は復員後、新潟医科大学にゆかれ再び医学を究められ、名医として名を挙げたが、自らも癌に冒され有為な生涯を残して早逝された。
惜しい戦友、医学者を失った。

十六連隊が当時位置したタリンゴンのマンゴ林
十六連隊主力は連隊本部をタヂン集落西方のマンゴ林におき、前面部隊はタリンゴン・カランジョン集落に陣地を構築、交戦した。
敵は既に我々の陣地と至近距離にあるイラワジ河のミンム対岸を渡り、カレワに進出して来ている。
敵は完全に制空権を持ち観測機によって偵察、戦闘機をもって銃爆撃をする。
地上にあっては長距離砲をもって息つく暇もなく射ち込む。
前面には戦車をもっての攻撃、まさに空陸を立体化しての円筒形陣地の構成である。
隠れ場所のない平原の戦闘で損害は甚大である。

ビルマ・タリンゴン集落の弾痕
イラワジ河畔の大会戦の最中、勇兵団はビルマ方面軍の総予備隊として決戦に欠くことのできない兵団の筈である。
ところが南方総軍は突如、早急に仏印の防衛を強化充実する必要に迫られているとして勇兵団を仏印に転進させることを決定、二十年三月十日にタリンゴンより撤退命令、イラワジ河は勿論、ビルマとの別れとなった。
今でもこのことが不明不可解である。
ガダルカナル島の場合、第一線より後退の際、命令はカミンボで補充部隊の充足をして再度攻撃に出るのだと伝え、内容はガダルカナル島よりの撤退であった。
ビルマの場合、勿論全軍一挙の撤退は出来るところではないが、仏印は本当に防衛強化の必要があったのであろうか。
もしそうだとすれば、どこから誰が仏印を侵略しようとしているのか。
インパールをはじめ断作戦に敗退し、いまイラワジ河畔の戦闘も勝算なしということでビルマ全軍撤退のためなのか。
当然撤退するにしても後衛部隊を残し、撤退部隊を援護しなければならない。
いずれにしても今でも我々の仏印進駐の意図は明確ではない。

ビルマ・メイテクーラ附近の旧戦場で無心に遊ぶ子ども
仏印へ転進
勇兵団の転進がイラワジ河畔の会戦に大きな痛手となった。
三月十日といえば陸軍記念日である。
イラワジ河畔の戦闘はタリンゴンの場合、周囲はサボテンや三メートル位の樹木の垣根に囲まれ、戸数五十戸位の小さい集落である。
この集落内に部隊が入れば銃砲火の集中を受けるので、寺院とか墓を楯にするか集落の周囲に壕を掘りめぐらして防御陣地を造り、しかも原野の陣地は一ヶ所だけには頼れないので、ときどき壕を換えなければならない。
この頃になって後方からの食糧補給も満足ではなく、体力も弱り簡単に壕も掘れない作業であった。
このように戦線を離れたが、敵がその後一挙に攻め込んだら他兵団はどうなるのか。
いずれにしても日本は今、中国、南海各地の広範にわたる戦線である。
点の戦域ではない。
この戦線を転進するにしても堂々と汽車や自動車で撤退するわけにはゆかない。
愈々転進の行動である。
勿論夜の暗闇を利用して集結地点をカローに決め、各部隊の各個前進である。
先ず難関はマンダレー街道であった。
同郷で私と一緒に手を繋いで入営した藤田重雄君が、このマンダレー街道を横切るとき、機関銃の掃射を浴びて即死した。
我々を含めて他部隊はさして損害もなくカロー集結することができた。
しかしこの間、サボテンばかりの砂漠地帯で飲料水もなく、約三日は指の先まで呼吸の脈が響く状態であった。
もう一日水がなければ脱水死をしたのではないかと思われた。
サボテンを切って樹液を吸ってもあの渋さでは喉が通らない。
井戸のあるところには敵が居て近づけない。
幸い夜半にひとつの井戸を見つけて救われた。
山岳地帯を歩いてシャン高原に出た。
目標はロイコー〜モールメンである。
我々がシャン高原を歩く頃、ラングーン、マンダレー、その他の地域にこんなにも多くビルマの地へ来ていたのかと思うほどの日本人達が後になり先になり従い来る。
敗戦の危機を悟って安全地帯を求めて来たのであろう。
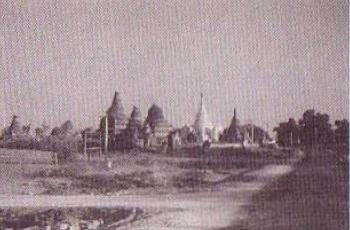
インパール屍街道
しかも気の毒なのは一般邦人が大きい荷物を背負って歩く。
その中には使えない軍票も詰め込んである。
言って聞かせても分からない。
命を懸けて働いたお金(お金といっても日本の軍政下にあれば使えるが、当時は既に通用しなくなっていた)なのである。
ビルマの最前線まで来たこの人々には格別の悲しさがあった。
シャン高原は平和な時に旅行をしたら美しい自然を楽しめることであろう。
落伍は即、死を意味する。
中にはマラリア等にかかり、樹の根元に座って観念したかのように動けない者も随分といた。
食糧はまったく携行していなかったが、途中現地人の住家があり、主として赤い餅米のような、しかも案外口に合う米が随所にあって、籾をとり飯盒で炊いて食べた。
後でこのルートを通った人達は既に米がなくて困ったそうである。
水牛や犬を見つけ次第に食った。
ガ島に続く二度目の敗戦行軍である。
途中敵に遭遇することもなくタイ国へ辿りつくことができた。
『七月十日バンコック到着。七月二十二日泰印度支那国境を通過、ビンホア州論譚に到着』
ロンタンは我々第二師団の墓場だと言われた。
もうこれ以外の地に退却するところはないからである。
サイゴンを取り巻く北方地域に連隊本部、通信中隊、連隊砲はホンカン、第一大隊はツドモウ、第二大隊はバツメオ、第三大隊はロクニンにそれぞれ分屯をした。
南部印度支那の防衛任務である。
第二師団は、ビルマ方面軍にとって唯一の方面軍総予備軍であって、勇兵団を引き抜いてはイラワジは戦えない。
従って勇兵団の転用は即時取り止めて貰いたいという切なる要請を却下して、早急に仏印の防衛を強化充実する必要があったということは前にも述べたが、仏印に来てみると緊迫した現地の状況は更々もない。

インパール敗戦の兵達が目標とした「オッパイ」パゴタ
終戦
運命の日、敗戦は八月十五日であるが、十六連隊将兵の戦時名簿には九月二日終戦となっている筈である。
従って八月十五日には我々は何も分からず、ロンタンにおいて討・原・光各兵団より補充を受け連隊の再建業務を行っていた。
九月二日、サイゴン師団司令部より集合の命令で私も随行し、サイゴンに出張した。
本日はこれより天皇陛下の玉音を放送するというお達しがあり耳を傾けた。
ザーと雑音と共に聞こえる声は確かに天皇陛下のお声だと分かるが、意味がよく聞き取れない。
ただ「万斛の涙を呑んで」というところは、はっきりと聞き取れた。
隊に帰って検討をしたが、聞きに行った命令受領者の誰しも終戦を告げるお言葉だと断定する者はいなかった。
一掃奮励努力せよ、ということではないかという解釈に落ち着いた。
しかし、その日の夕方正式に終戦、日本は無条件降伏をしたということが示された。
無条件降伏ということがどのような内容で、今後どうなることか誰も分からない。
しかも戦争が終わったということだけでは何か空しさだけが頭の中に残り何事にも手がつかない。
時間が経過していくに従って我々の軍隊は、国家は、同胞、家族の運命はどうなるのであろうかと思うと戦争をしているときよりも気が重く、虚脱状態になっていく。
過ぎ去った、ジャワ作戦において降伏したオランダ軍の状況とは違った意味の敗戦である。
彼等は局地軍の敗戦であって本国が降伏したわけではない。
だが我々は国家全体が負けたのだ。
今更のようにジャワにおいてオランダの将校が、日本はこの戦争に勝てる筈はないと言った言葉が思い出された。
それから数日ならずして捕虜として扱ってきたフランス軍と立場が逆転して、彼等が戦勝国として我々を管理する立場になった。
日本の降伏によって民族意識に目覚めた仏領印度支那国民は、民族独立のための組織、越盟党の活動を活発化した。
終戦後であっても九月二十八日にはその状況が険悪になったということで、連隊本部は第一中隊と共にツドモウに移り、警備をした。
越盟軍に対し、日本軍は警備、或いは暴動の鎮圧を命ぜられるが、彼等は日本軍をターゲットとして戦う意志はなく、度々接触の機会を持った。
ただし十一月四日に第三大隊長辻田少佐が巡視中、中越軍の急襲を受け負傷する事件があった。
軍旗奉焼
敗戦、しかも無条件降伏ということで今後国際法に従って事が処理されてゆくことになるであろうが、連隊長の憂慮されることは軍旗の処理である。
軍旗は一般の公共物件ではなく、陸軍成規類聚にも規定のない天皇より大元帥という職階の許、天皇の名代的存在の位置を占める。
したがって天皇陛下の指示により処遇すべきことが本来の姿であろう。
しかしその余裕もない。
絶対敵の手に渡すべきものではない。
私は事務的にはそのように進言を申し上げた。
結論は連隊長の責任において腹を切るつもりで最善の方法をとるべきということで、敵将が進駐してこない事前に奉焼すべきと方針が決まった。
新発田歩兵第十六連隊の軍旗は明治十七年八月二十四日、連隊に左の勅語とともに授与されたものである。
勅語
歩兵第十六連隊編成成ルヲ告ク仍テ今其隊旗一流ヲ授ク汝軍人等協力同心益々威武ヲ宣揚シ我帝国ヲ保護セヨ
初代連隊長歩兵中佐山本清堅は左の如く奉答した。
奉答
敬テ 明勅ヲ奉ス 臣等誓テ国家ヲ保護セン
軍旗は、国旗と同異議のところ(国)もあるが、それ以上に、その存在価値は尊厳なるものがあった。
国家存在の基本である国防は軍隊組織である。
軍旗はこの組織の中心的に象徴として人身を収欖し、団結を強固なるものとするため神聖な程に心の寄りどころであった。
過去多くの戦役において将兵と共に戦野を駆け、風雪に耐えて傷々しく、旗竿・竿頭・それに旗部分は周囲の房だけになっている。
この伝統に輝く軍旗も敗戦という事実に命運が尽きねばならないのか。
しかも我々の目前で。
絶対に敵に渡してはならない。
既に我々の軍刀は献刀式という形式で英軍の手に渡してある。
その他の武器も一切解除している。
特に連隊長の胸の中は、自分が切腹するに等しい悲しみであろう。
協議の結果、奉焼することに決定された。
中田中尉を旗手として五名の軍旗護衛兵をつけて秘かな奉焼となった。
六十有余年の歴史を閉じたのである。
ただし竿頭と房などの残っている部分は、極秘裡に分解して故郷に持ち帰る。
そして後日必ず集めて出来る限り復元させたいということを申し合わせた。
今次の大東亜戦争には軍旗の危機とさえも思わせた場面があった。
ガダルカナル島撤退時は武田少尉の必死の護衛で奉持することが出来た。
昭和二十年九月十日、歩兵第十六連隊の軍旗は静かに歴史を閉じた。
この軍旗は現在、新発田の陸上自衛隊第三十普通科連隊舎の旧白壁兵舎に戦史資料として大切に保存されている。
祖国へ
十月二十三日、ロッタム准将を長とする英印軍は越盟軍の妨害を受けることなく順調にツドモウに進駐した。
この時期、処々に植民地から独立する越盟軍の活動が活発化した。
十二月五日、ツドモウに於いて降伏式、献刀式と武装解除が行われた。
連隊長以下帯刀本分者は英国騎士道に則った献刀式であった。
英印軍で武功を樹てた軍人(私の場合は軍曹であった)に自分の刀を渡す。
他の武装は目録をつけて一括渡した。
武装解除後のサイゴンでは一般邦人がフランス人に迫害されて困るということで、我々のもとに救いを求めて来た。
軍隊としての我々に対するものなら未だしも、非戦闘員に対する迫害は許せない。
そこで師団首脳部及び連隊としては、戦争で負けたとはいえ、フランス軍となら、たとえ武器が無くとも戦う方法はあるので一戦を交えようということになった。
その場合、英軍に及んではならないので、英軍に理解を求めたところ、自分達が責任を持って日本人を護るから戦闘行動は中止するようにとの仲裁があり落ち着いた。
以降情勢は大変良くなった。
印度支那は長年、フランスの植民地として統括されてきた。
そのため国名も仏領印度支那となっていた。
それが大東亜戦争を契機として印度支那の国民は民族意識に目覚め、独立のため独立軍の創設、戦闘へと進んでいった。
一方、我々日本軍は確たる情報ではないが、日本には既にソ連軍が来て婦女子を連れ去ったとか、帰すと言って船に乗せるがフィリピンの沖に行くと沈めるとか、敗戦日本がどうなっているのか、どうなってゆくのか分からない混乱状態にあった。
そこに仏印の独立軍が「いままで日本軍に大変御苦労をかけたが、今度は我々の力で独立します。出来ることなら力を貸してください」と夜間、密かに誘いに来る。
身分上のことや生活も保証します、と言う。
日本に帰っても希望が無い、敗戦の祖国に帰って苦労するよりも、ここで男一番やるかという若者達、色々な事情や考え方、環境があって連隊で二十五名程離隊していった。
愈々帰還が決定したとき、私は十名位の人員をつれてクラチエ(現在のカンボジア)まで行ってこれらの人と話し合った結果、半数は戻ってこなかった。
私の同集落で私より一級下の本間民四郎君も遂に戻らなかった。
この人達はフランス軍の密告に対する褒賞金により全員が亡くなったと聞いている。
昭和三十三年、最後の処理として福島県棚倉町の小林満君の件がある。
母親が八十歳を越えていつ死ぬか分からない。
是非その前に満の墓を造ってやりたいので手続を頼みますという切々たる手紙が数回に及ぶ。
それで私は厚生省に出向き、私の軍隊当時の職歴を言って、私が証人となるということで戦死の手続をした。
従って連隊最後の復員完結は昭和三十三年となる。
日本に帰還が決まりかけた一月十九日、連隊主力はアプオントリーに集結待機し、現地自活に入った。
英軍の好意により、我々が密かに蓄えていた米は没収されることなく確保出来た。
兵の中には大工さんも居るので、連隊長の仮住まいは立派な家が建った。
そのまま置いてくるのが惜しいようであった。
土地は肥えており、野菜、根葉等なんでもよく出来て不自由することはなかった。
復員事務としてのこの待機の間は、生存者の戦時名簿、事実証明、現認証明書等帰還後身分や傷病を証明する書類を整備するには助かった。
事務をとった書記の皆さんに感謝したい。
愈々帰還決定になって二つの問題があった。
ひとつは越盟独立軍に行った人々のこと。
半数は戻ったが残った人達のこと。
ひとつは乗船に際して戦犯者探しの面通しが行われるという厄介なことである。
十六連隊としては戦争中、現地人や捕虜に対し虐待行動を加えたとか、人権侵害をやった事実はないのだが、実は数ヶ月前、他部隊から転属をして来た将校がおられた。
戦犯捜査を免れるための転属らしい。
人事係としては普通の転入者として扱っているが、戦争という異常な環境の中で、どこまでが犯罪行為なのか。
既に検分をしたいという人達が聖雀(サンジャック)港に来ているという。
我々は白人を見てもあまり見分けはつかない。
仮に相手が間違ってこの人だと指を指されれば、違いますと言っても文句なしに犯人にされるのではないか。
それぞれに身に覚えがないといっても心配される。
結果として全員無難に乗船することが出来た。
乗船は仏印・聖雀港である。
奇しくもジャワ作戦の際に船団を組んで出陣したのが、このカムラン湾であった。
同じ港から出発をして、いま再び同じ港から故国に帰る。
何か因縁らしいものを覚えた。
乗船、そしてフィリピンの沖に来た頃、夜空に輝く南十字星も消えて、北斗七星が見え出す空に向かって、船の甲板上で誰が吹きならすか尺八の音、江刺追分が郷愁を誘うかのように朗々と流れる。
恐らく現地の竹で作った尺八であろう。
祖国に想いを馳せれば暗くなる。
喜べない心境になる。
私自身のことも全く見当がつかない。
青春を戦争に燃え尽くして三十路の年齢で、これから何をどうすべきか。
想えば十年前、不況の農村から逃げ出して満州にわたり、軍隊という組織の中で身を抜くことも出来ず、激戦場を生き延び、再び故郷に帰る。
印度支那に残ることも考え、手段もとったが、責任上残れなかった。
身命にかけて祖国防衛のために戦ってきたが、これからは生きて再び、命がけで国家再建のため祖国に向かっている。
日本民族は永遠に滅び去ることはないのだと信じつつ。
五月二日聖雀港出港、同月十二日大竹(広島)港着。
夢のような生還。
上陸と同時に、戦場にのみ対峙した米軍が上陸後における各種の検証をやっていた。
通訳を通じてこの部隊のオフィスはどこかと言って私のところに三人の米兵が来て、その場で書類の入っている公用行李全部に封印をして接収された。
私は非戦闘員ということで他の戦友が服装検査をされたようなこともなく通された。
米軍の組織機構に準じたものらしい。
接収された連隊の各種資料は、アメリカの戦史資料として現在も保管されているという。
戻す方法はないものかと交渉をしたが、行けば見せるが返すことは出来ないという。
無条件降伏の条件の中での武装解除と同じ扱いなのかどうか、訊いてみたいと思う。
入港に伴う防疫や諸手続も終わって、格別な解散行事を行うことも出来ないまま、あっけない自由解散。
昭和二十一年五月十三日、復員完結という終止符を打った。
そして混雑する列車にそれぞれが故郷に向かって別れた。
感無量なり。
















