日本陸軍 第二師団 歩兵第十六連隊 新発田 あやめ会 戦記 戦死者名簿 ガダルカナル 雲南 ビルマ ジャワ ノモンハン 遺骨収集 政府派遣
暗黒の孤島に遺骨を求めて5
南十字星の下に ガダルカナル遺骨収集
"暗い記憶"たどる すっかり変わった風景
はるかな島
日本から五千五百キロかなたニューギニアの東側の南太平洋に浮かぶ群島は、ジャングルにおおわれた未開の地であった。
スペインの探検家アルバロ・デ・メンダナが、このサンゴ礁の島々を発見し、白人として初めて足を踏み入れたのが一五六八年。
夢と空想にとりつかれていたメンダナは、旧約聖書にあるソロモン王の"宝の島"と信じ込み、ソロモン諸島というすばらしい名前をつけた。
しかし、そこには財宝などあるはずもなく、人食い人種の住む地の果てだった。
その後、支配権を握ろうとする白人と、侵入者を嫌う原住民との間に、血なまぐさい殺し合いが続いた。
スペイン語で"海峡の墓"を意味するガダルカナルの島名は、その歴史的事実を伝えている。
ガダルカナル、南緯九度、東経一六ゼロ度の南冥(なんめい)にひっそりと存在する。
面積六千五百平方キロ、新潟県の半分くらいのこの島。
太平洋戦争が起こらなかったら、日本と何の関係もなく、その名は私たちの口にものぼらなかったであろう。
昭和十七年八月七日の米軍上陸から翌十八年二月七日の日本軍撤退まで、ちょうど半年間にわたる激しい飛行場争奪戦が繰り広げられた。
真珠湾の奇襲いらい、連戦連勝に酔っていた日本軍は、海のミッドウェーに続く陸のガダルカナルで、初めて苦杯を舐め、戦局は米軍有利へと展開するきっかけとなったのである。
制空権を握られ、補給を断たれたガダルカナルの日本軍は、悲惨のきわみであった。
飢えにマラリア、赤痢などの病が重なり、死者の出ない日はなかった。
上陸した約三万二千の将兵のうち、死んだ者は約二万一千人。
さらにそのうち一万三千人が餓死と病死と記録されている。
第二師団に所属した新発田歩兵第十六連隊はじめ、わが郷土部隊も約二千八百人を失った。
"海峡の墓"は二十世紀になって突然その不吉な名を復活させた。
「ガダルカナル島は単なる島の名ではない。それは帝国陸軍の墓地の名である。」ー軍事評論家の伊藤正徳さんは、その著「帝国陸軍の最後」の冒頭に、こう書いている。
ガ島はまさに"餓島"であった。
「待っていろよ。必ず迎えにくるからな」。密林や海岸に横たわる遺体、身動き出来ない戦友を残し、後ろ髪引かれる思いで島を去ってから、二十九年近い歳月が流れた。
なんとかして、もう一度島へ渡り、なき戦友との約束を果たしたい。
生き残った人々の間に、遺骨収集団派遣の努力が続けられた。
「どうしていままで放って置いたのか」と、遺族は国に不満をぶつけるが、長い空白ののち、とにかく待望の日が来たのである。
収集団は、政府派遣の厚生省担当官四人に、第二師団関係の新潟、福島、宮城の計四十名、第三十八師団関係の愛知、岐阜、静岡、三重などの計二十二名が協力をする形をとり、本県からは生存者、遺族、報道の十六名が選ばれた。
「帰還してからこの方、戦友の戒名を過去帳に記し、毎日供養を怠らなかった。どんな
に待っていることか・・・」
出発前から、早くも涙ぐむ団員。
思いはみな同じであった。
十月十二日午後五時、羽田を飛び立ったカンタス航空のボーイング707は、香港、ダーウィン(オーストラリア)を経て、ポートモレスビー(パプア・ニューギニア)の熱風の中に舞い降りた。
ここでオーストラリア航空のフレンドシップに乗り換え、めぞすガダルカナルの島影が見えたのは十三日の昼過ぎ。
スチュワーデスの知らせで、機内は一瞬騒然となり、そして静まり返った。
小さな窓に顔をすりつけるようにしてむ、じっと見下ろす目、目・・・。
旅客機は、日本軍が撤退した島の北西端、エスペランス岬から北海岸に沿って東進していた。
郷土部隊が上陸したタサファロングから、やがてホニアラの町が見えてきた。
海岸の椰子林にのびる白い道路、緑の丘に建ち並ぶ青い屋根、白い屋根。
「変わったなあ」と、だれかがつぶやいた。
必死に"暗い記憶"をたどろうとするが、眼下に展開する明るい景観とは、どうしても重
ならないようすであった。
ホニアラのヘンダーソン飛行場に着いたとき、団員たちの昂奮は収まっていた。
「ようこそソロモンへ」と、観光客なみに花輪をかけられ、その甘酸っぱい香りが気勢をそいだこともあった。
だが、この飛行場こそ、日米攻防のかなめとなったところである。
空港から、直ちにバスでタンベアの宿舎に向かった。
戦後の新興都市、ソロモン政庁のあるホニアラを通り、椰子の植林を走る。
第一次ソロモン海戦などで、多くの艦船が藻屑と消えたアイアン・ボトム・サウンド(鉄底海峡)が行く手に広がる。
想い出は徐々によみがえる。しかし、それと同時に「うまく収骨できるだろうか」という不安が、ふと胸をよぎるのだった。
欠いた意思疎通 戦場は"南海の楽園へ"
戦友を求めて
大勢の人たちが、ひとつの目的を成し遂げようとするとき、初めから終わりまで、そう万事うまくゆくものではない。
今度の遺骨収集にしても、スタートから予期しない出来事が続き、ずいぶん団員を困らせた。
政府の"公式派遣団"は厚生省の役人だけで、本県をはじめとする派遣団は、あくまで自主的な協力の形をとらされた。
「かってにおやりなさい」ということで、国からビタ一文金をもらったわけではない。
厚生省の石田武雄団長(援護局業務第一課長)らは、九月末にはやばやと現地に乗り込んだので、協力団にしてみれば、事前にかなりの情報集めと準備が出来ているものと期待した。
ところが、政府派遣団はガダルカナルのほかにソロモン諸島の全域と、その北側にあるギルバート諸島の遺骨収集も兼ねていた。
そのため、せっかくガ島の情報を集めた係官が、協力団の到着したときはギルバートへ飛んで不在だったり、かなり意思の疎通を欠く面があった。
「早く来て、なにをしていたのか。これじゃあ二重手間だ」と協力団の不満の声も聞かれたが、正面きって言い出せないことでもあった。
ハプニングは続いて起きた。
本隊より二日早い十月十日に出発していた先発隊が、ポートモレスビーのゲートで手を振っているではないか。
「もう南洋ボケになったかな」と目を疑ったが、気象条件が悪かったためはるばるオーストラリアのシドニーへ飛び、そこから逆戻りしたという。
モレスビーに着いたら、ガダルカナルへの連絡便がなく、結局、本隊と合流するハメになった。
「お役に立てなくて、なんとも申し訳ない」先発隊の長谷川栄作さん(五四)=北蒲原郡聖籠村助役=は頭をかいたが、不可抗力では仕方がない。
モレスビーから出発の段になって、また問題が起きた。
荷物の重量が制限を超え、「これでは飛行機が落ちてしまう。人を五、六人残すか、荷物を降ろせ」と航空会社の係員。
「そこをなんとか・・・」と頼んでみても、"まあまあ"の日本流は通用しない。
共同装備と、個人のトランクを一部残すことにしたが、すぐに貨物便で送る約束が、四日後にやっと到着した。
収集団派遣県実行委員長の横山義三さん(五三)=新津市・製材業=らは、着の身着のままでしばらく作業に当たる気の毒なことになった。
次の障害は、ガ島の玄関、ホニアラ空港の税関である。
黄色いビニールシートで包んだ、収骨作業用の備品が目を付けられた。
「これはなんだ。あけて見せろ」
「収骨作業に必要な品物だ。日本とソロモン政庁の間で了解がついているはずだ。通してくれ」
「調べるから、二十四時間ストップだ」
黒い顔に緑のベレーを載せた現地人の税関史は、ことさら威厳をつくってみせる。
いくら理を尽くしても返事は「ノー」の一点張りだ。
後で聞くと、資源の乏しいこの国では、輸出入税が有力財源になっている。
デカい荷物を持ち込んだ収集団は、願ってもないお客さんだったのだ。
医薬品、水筒、懐中電灯、うちわ、収骨袋などに税をかけられ、トランジスタラジオなどは、もう一個買えるほどの金額を徴収された。
ようやく宿舎に落ち着いて、次に心配になったのは島の変わりようである。
かつての"地獄の戦場"は"南海の楽園"と化している。
三昔も前の記憶にたよっていた団員たちは、自信を失いかけていた。
さっそく会議を開き、行動計画について話し合った。
同じ協力団といっても、第二師団の新潟、福島、宮城、それに第三十八師団とでは、それぞれ思惑が微妙に異なる。
自分達が命をかけて戦った場所へ、まず行きたがるのは人情である。
「ここだけはおれたちの手で」との執念もある。
へたをすれば、感情的に対立することにもなりかねない。
悪いことに、亀岡高夫協力団長(福島県選出衆議院議員)が国会の関係で、参加出来ないことになった。
それだけに、各県の班長はチームワークの調整に、ことさら気を配った。
まず収骨地点を選ぶため、初日は偵察に出ようと決めた。
十月十四日、タンベアからマイクロバスやトラックに分乗して、かつての戦場をめざす。
前日来た椰子林の道を逆にたどり、野戦病院のあった水無川、第二師団の本拠であった"丸山道"の入り口、日米両軍がにらみ合ったホニアラの丘。
最後の激戦があったオーステン(アウステン)山(四一〇メートル)の中腹まで登って展望した。
そして郷土部隊が夜襲を敢行した丘とジャングルと草原を歩き回った。
「ルンガ飛行場夜襲のとき、確かあのジャングルに沿って進んだ」と佐藤典夫班長(五五)=県農産普及課長=が指さす。
「間違いありませんね」と杉林清蔵さん(五三)=新潟市・東北電力社員=、吉井邦夫さん(四九)=五泉市・メリヤス製造業=。
激しい十字砲火の中で、九死に一生を得た人たちだ。
こうして現地を歩いて、一つ一つ記憶は確かめられていったが、さて戦友の遺骨はどこに、収集はどうやって・・・となると、まだ途方に暮れる状態だった。
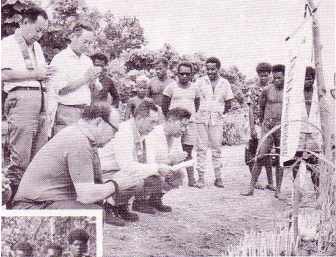
ルンガ旧飛行場での慰霊祭、物珍しそうに見守る現地人。

小川、沖川地区の収骨後の慰霊祭で読教する矢嶋大僧正。
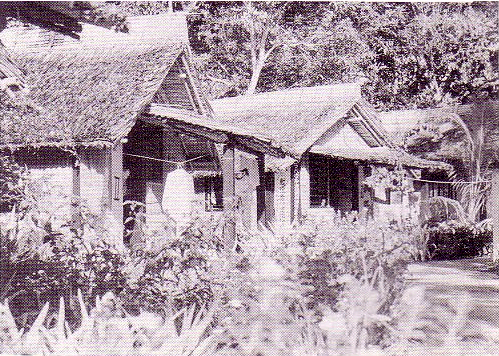
一戸に3〜6人宛泊ったバンガロー、リゾートホテル形式で、たんべあビレッジと呼ばれる。

毎日の日課、器材点検出発準備
悲し"無言の対面" 散乱する朽ち果てた遺骨
ルンガの祈り
ガダルカナル半年の戦いといっても、毎日砲火を受けていたわけではない。
ヤマ場ともいうべき大きな攻防が幾つかあった。
中でも最大の激戦はルンガ飛行場の夜襲である。
ルンガというのは日本軍の呼び名で、現在ホニアラ空港になっているヘンダーソン・フィールドのことである。
ガ島の米軍など、ほんのひとひねりと甘く見ていた大本営にとって、頑強な抵抗は意外だった。
一木支隊(旭川)がテナル川で全滅、川口支隊(久留米)がムカデ高地で敗退したあと、あわてて当時ジャワにあった第二師団の投入を決めた。
昭和十七年十月六日から十四日にかけて、連合艦隊の支援のもとにタサファロングに上陸した新発田歩兵第十六連隊をはじめ第二師団の精鋭は、大本営派遣の辻政信参謀の作戦指導に従って夜襲を決行した。
物量にものをいわせ、火力にまさる米軍との正面衝突を避け、オーステン(アウステン)山の裏側を廻って、飛行場の背面から一気に襲いかかる作戦である。
一口にそうはいってもジャングルや険しい谷間に工兵隊が、急造した"丸山道"(丸山政男第二師団長の名前をつけた)を一列縦隊で約三十キロ、一週間の強行軍はきついものだった。
そのうえ隠密行動をしたはずなのに、すっかり米軍に読み取られていた。
ジャングルに張りめぐらしたマイクロフォン陣地につかまり、迫撃砲や機銃で徹底的に叩かれた。
十月二十四日、二十五日の夜襲で広安寿郎十六連隊長、古宮正次郎二十九連隊長(会津若松)はじめ、戦死者約五千人。
「与えられたのは航空写真が一枚。地図もなく、敵情不明」「着いたときは疲労のきわみ」「迫撃砲弾が正確に、雨のように降ってきた」---
生き残りの証言は、それがいかに無謀な作戦だったかを物語る。
「隣の戦友がバタバタと倒れる。ひとつ間違えば、私自身が骨を拾われる立場にいた」。
阿部茂さん(五五)=新潟市・収骨団派遣県実行委員事務局長=も、佐藤元春さん(五五)=豊栄市・自転車販売業=も、運命のいたずらをじっとかみしめる。
郷土部隊にとって、うらみも深いそのルンガへ、まず本県派遣団の足が向くのも当然であった。
収骨の行動初日である十月十五日「骨のある場所を知っている」というジェジェス村のエドワード、ローリンの二少年の案内で、前日偵察した草原を横切り、ジャングルに沿ったイモ畑に着いた。
ここはもともと密林であったところだが、開墾したときに骨を見つけたらしい。
少年の指さす切り株をみると、そこに一握りほどの遺骨があった。
風雨にさらされ、枯れ枝と見誤るように変わり果てた兵士の亡き骸が・・・。
長い間、待ち望んでいた遺骨との対面にしては、なにかあっけなかった。
「どっちだ」「まだ見つからないか」。
それまで声を掛け合っていた団員たちは急に黙り込んだ。
無表情にじっと骨を見つめ、それから手を伸ばして骨を拾い、袋に収めた。
「ここにもあるぞ」
一団が風のように、さあっと動く。
別の切り株の上にまた一体。
案内の少年たちが拾い集めて置いたのだろう。
突然、佐藤典夫さんの目に涙が光った。
大きい体の小林誠司さん(五二)=長岡市・国鉄職員=も、手を合わせながら泣いている。
「待っていたろうな」長谷川栄作さんがポツリと一言。
「こんなボロボロになって・・・」と大地松蔵さん(五八)=佐渡相川町・町議=。
こらえていた感情が、せきを切ったようにほとばしった。
誰の骨かはわからないが、ルンガの戦死者の遺族から托された写真、手紙、ウィスキーなどを供え、線香を手向けて冥福を祈った。
それから穴を掘って供物を埋めた。
黙々と作業する団員たちの間に、ようやくなにかホッとした空気が流れた。
「四十体ほどある」と思い込んだのは、四十片の聞き間違いで、この場所での収骨は二体にとどまった。

確認した夜襲地点に向かって遺骨の捜索を始めた。

ルンガ飛行場跡で最初に発見した遺骨。
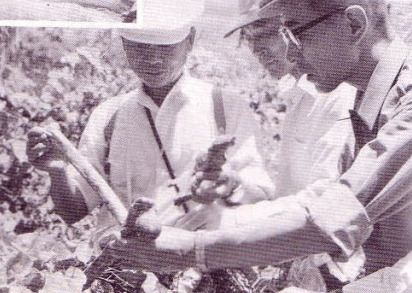
感 無 量。
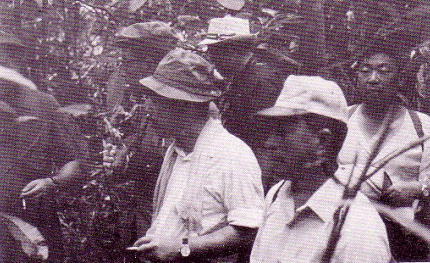
昼なお暗いジャングル内の捜索を終わり一服(旧飛行場附近)
やはりジャングルに踏み込まなければ、多く捜し出すことは出来そうにない。
日を改めて出直すことに、衆議一決する。
野戦病院のあった水無川の収骨に全力を投入したのち、二十日再びルンガへと向かった。こんどは村の酋長直々の案内で密林へ突入した。
昼なお暗いジャングルは、風もなく蒸し暑い。
ブッシュナイフで木の枝を払いながら、足早に歩く原住民についてゆくのは一苦労だ。
遺族代表の一人、佐藤敬義さん(五八)=岩船山北町・本間組千葉支店長=も懸命に歩く。
額から、首筋から、背中から吹出す汗で、シャツもズボンもびっしょり。
トゲのあるつるが顔をなで、木の根に足を取られてもんどり打つ団員もある。
広葉樹の葉が積み重なって、じめじめした地面に、墜落した米軍機のプロペラや、鉄カブト、飯盒などが散らばり、半ば埋もれている。
ところどころあるクボ地は、砲弾の洗礼から逃れようと、日本軍が掘ったタコツボの跡。
遺骨は、あっちに一体、こっちに一体と広範囲に散乱していた。
なかなか収骨の能率があがらず、苛立ちさえ覚える。
ある遺骨は、大木の根元に寄りかかるようにして、迎えを待っていた。
側に手榴弾が一個。
夜襲に失敗して撤退の際、傷ついて動けなくなった戦友のため、いざというときの自決用に置いていったものだろう。
それを使うこともなく、息を引き取った兵士。
消えゆく戦友の足音を聞きながら、たった一人で取り残されたときの心境は、どんなであったろう。
まぶたに浮かんだのは、母の顔か、故郷の山や川であろうか。
あたら青春が、異郷のジャングルに虫けらのように果てる。
報われることのなかった戦斗の空しさ。
孤独な戦士との対面に、目頭が熱くなり、胸が締め付けられた。

激戦地のジャングルに向かい、なき友の位牌を立てて、ささやかな慰霊祭を営んだ。
読経も嗚咽に 遺骨、層なして五百体
水無川の墓標
土の中から出てくる遺骨は、土と同じ色であった。
掘り起こすとボロボロと崩れ落ちる骨もあった。
最も形をとどめていたのは大腿骨。
"しゃれこうべ"は、前に原住民が拾っておいたものを含めても、数えるほどしか見つからなかった。
シートの上に、そっと安置される無名戦士たちの骨。
汗にまみれ、疲れも忘れ、団員たちはとりつかれたかのように掘った。
ここは野戦病院のあった水無川の谷である。
現地ではポハ川と呼ぶところ。
ホニアラの町から海岸沿いに西へ約十キロ。
そこから石のゴロゴロとした川原を二キロさかのぼる。
衛生司令部の置かれた大きな洞窟も、そのまま黒い口を開いていた。
さらに五百メートルほど行くと、病院跡と戦死者の遺体を始末した"死体投棄穴"の場所に着く。
この一帯を管理しているボロスグー村のギリアン酋長に協力を求め、遺体のありそうな位置を教えてもらった。
ヤシやビンロウジュやタピオカイモの林に囲まれた、小広い草地であった。
「ここに間違いない。日本兵の骨、いっぱいあるよ」という。
「みつかってくれよ」と祈る気持で、早速シャベル、クワを使って穴掘り作業に取り掛かる。
まず表土を三十センチほどの厚さで取り除き、一堀、二堀するほどに、遺骨が続々と出てきた。
三十年近くも土中に埋まっていた遺体は、原形をとどめているものもなければ、においもしなかった。
まるで気の根っこや、イモのようだった。
それが層になって出てきた。
戦いのさなか、次々と死んでゆく兵士たちの処置に困り、穴を掘っては投げ込んだものだ。
平和な時代になったいま、黄色い膚の日本人と黒い膚のメラネシア人が、ぎらつく太陽の下で、それを再び掘り返す。
考えてみれば、それは異様な情景だ。
「なぜもっと早く迎えにこれなかったか。
国のために死んだのに、慰霊さえもなおざりにする。国の仕打ちは冷たすぎる。」遺児として参加した渡辺和春さん(二九)=新発田市・会社員=は、変わり果てた骨を掘りながら憤り、嘆いた。
「この中に、ひょっとしたら父もいるのだろうか・・・」とつぶやきながら。
半日の作業で百体くらいも収骨できたろうか。
昼休みに、早速団旗を立て、即席の供養塔をつくった。
霊前に位牌、手紙、故人の好物だったという酒、水羊羹の缶詰などを供え、ロウソクに火をともして合掌する。
"南無妙法蓮華経"の袈裟を肩に掛けた清水左忠二さん(五三)=三島越路町・飲食業=が、土の上にべったりと座り、静かに読経を始めた。
急に声が詰まった、言葉にならない涙声の経文が、水無の谷に流れる。
「タコツボの中で砲撃を受け戦友がみんな傷つき、死んでも私だけ無傷で帰れたのですよ。きっと供養の役目を仰せ付けられたのでしょう。これで、みんなの霊も浮かばれます。」
清水さんと同じ輜重隊だった小林誠司さんも、遺族から預かった手紙を供え、一心に祈りを捧げた。
二日がかりで水無川の収骨を終え、ここで悪路に収めたのは推計五百三十体、木の切り株に「水無川戦没者之霊」とマジックインキで書き、遺骨を安置して霊を慰めた。
「長い間ご苦労さまでした。
ありがとうさま。いよいよお帰りになるとのこと、喜んでお迎え申し上げます。あなたの兵隊の苦労を思うと、ただ黙祷して、なむあみだぶつと申すばかりです。
私も孫六人のあばあちゃんになりました」阿部茂さんが、新潟市の遺族、坂井ヨシさんから托された手紙を読む。
だが、声がつまって最後まで読み切れない。
「軍歌を歌おう」小林誠司さんの発案で、佐藤典夫班長が音頭をとる。
「赤い夕陽に照らされて、友は野末の石の下」
「さらばガ島よ またくるまでは しばし別れの」
少し調子っぱずれの合唱が繰り返される。
懐古趣味や戦争賛歌と、誰が笑うことが出来ようか。
それは、なき戦友への鎮魂の歌であった。
この"式次第のない儀式"の意味は手伝ってくれた黒い住民たちにも、よくわかる様子だった。
「日本人が、友達の骨を求めて、はるばるやって来た」と息を殺し身動きもせずに見守ってくれた。
近勇次ドクター(六五)=新発田市・元市長=は、水無の谷に四度はいった。
軍医中尉として、この野戦病院に勤務した想い出の地である。
「せめて薬品と器具さえあれば、助かる者もたくさんいた。
それを見殺しにしてしまって・・・病院とは名ばかり、まるで墓場だった」---責任を果たせなかった悔恨が、ドクターの胸を締め付けた。
すべてが終わったあと、一人静かに頭を下げたいという心情が、四度足を運ばせた。
「みんな、すまなかったなあ。一緒に国へ帰ろうよ」。
墓標の前で、いつまでも嗚咽が続いた。

水無の谷にいま、ようやく墓標が立つ。三十年近い遺族の願いをこめ、線香の煙がにおう。

原住民は、収集団の手足となって、よま働いてくれた。右側に立つのがボロスグー村のギリアン酋長。
住民の"稼ぎ時" 遠い部落から手伝いに
日当一ドル
ガダルカナルのかっての戦場は島の全域ではない。
争奪の対象となったヘンダーソン飛行場から、日本軍が撤退したカミンボ附近まで。
つまり、島の西北部の海岸線から平原、谷、丘にかけて長さ六十キロ、幅は広いところで約十キロ、狭いところで百メートル足らずの細長い地域である。
そのいたるところに遺骨が散乱しているから、収集の苦労もものであったことは想像していただけよう。
宿舎があるのは、カミンボよりさらに二キロほど西のタンベア。
郷土部隊の主戦場になったルンガは逆に東のはずれ。
ホニアラの町まででも、宿舎から四十キロ以上あった。
収集作業は、毎日トラック、マイクロバス、レンタカーなどを使って海沿いの国道を往復しなくてはならない。
新潟市を基点にして計ると、三条、見附、さらに長岡といった距離を行ったり来たりの形だ。
国道といっても、ホニアラの町から飛行場にかけての十キロたらずが舗装されているだけで、あとはジャリ路だ。
何本かの川を渡る。
橋はどれも一車線ぎりぎりで、タンベア近くの川は四本ほど橋がない。
玉石のゴロゴロした川原に降り、ザブザブと水に入ってゆく。
宿舎から町までは五十分くらいかかった。
通いなれた道でも、しまいにはいやになる。
それに晴れた日は、中天にかかる太陽がギラギラと輝き、気温が四十度近くまで上昇する。
日なたに長く出ていると、頭がくらくらしてくる。
収骨場所になる丘の上は照り返し、谷筋は風が死に、ジャングルの中ときたら湿気がひどい。
作業はいつも汗まみれである。
水が変わったため下痢になる団員、日射病で倒れる団員もあった。
日一日とたつと、やはり疲労も出てくる。
作業も終わりに近づいたころ、とうとう骨折者を出してしまった。
「一緒に帰国出来ないのでは・・・」と心配したが、付き添いの近ドクターとホニアラ病院の英国人医師の手当てが良く、ギブスを巻いて幸いだった。
いずれにしても、二十九年前の記憶をたよりに、気負い込んでいた団員たち。
しかし、長いブランクと島の変化は、どうしようもなかった。
最初はあっちにつまずき、こっちに迷った。
島に住む黒人たちの情報提供と協力が無ければ、おそらく十分の一の成果も上がらなかったろう。
今度の遺骨収集は、日本政府とソロモン政庁の了解事項になっていたため、収集団が島を訪れる一ヶ月くらい前から、ホニアラ放送がラジオで流していた。
だから現地に乗り込んだときには、山奥の部落までも、口から口へと伝わっていた。
国道を走っていても、行きかう黒人たちが、大人も子供も手を振り、好意的に迎えてくれた。
ことに、水無川でのボロスグー、ポハの協力ぶりには、団員みんなが感謝した。
打ち合わせておいた日、谷の入り口の国道ばたまで出迎え、シャベル、クワ、ナタなどの道具を担いで収骨場所まで先導した。
貫禄のあるギリアン酋長の指揮で、よく働いた。
作業は長く続けるとバテるから、三十分くらい働いては一休み。
「オーイ、休むぞ。そら、タバコをやるぞ」。
我が方の収骨班長、大地松蔵さんの号令も堂に入ったものだ。
声を掛け、手まねで合図すると黒人達が白い歯を出して集まってくる。
休むたびに、一人一本ずつタバコを分けると、たちまちなくなる。
「俺たちの吸う分がないぞ」と団員たちは大慌て。
現地語で休む事を"マゴ"というが、ここでは"シガレット・タイム"が共通語になった。
一日、二日と作業をともにしていると、親近感もわいてくる。
昼食時には、サンドイッチやライスボール(握り飯)、コカコーラを分け合った。ひとつの水筒から喉を潤した。
こうした住民の協力に対し、無報酬というわけにはいかない。
数年前に、米国から収骨にきたとき、日当一ドル払ったという話なので、右へならえした。
作業が終わると、一列に並ばせて、一ドル(オーストラリアドルで四百円)と日本から持ってきたランニングシャツなどのおみやげを手渡す。
ところが驚いた事に初め十数人だったはずが、いつの間にか三十人を越えていた。
仲良くなったトカニー君に聞いてみると「かなり遠い部落からも手伝いにきた」という。
"ジャパーニーズ"の骨拾いは、なにごともなく呑気に暮らしている原住民にとって"お祭り騒ぎ"であり、ちょっとした"稼ぎどき"でもあったのである。
住民がその気なら、こちら側としても大いに稼いでもらうことにした。
深いジャングルに覆われた丸山道など、遺骨があることがわかっていても、踏み込むのに躊躇するような難所もあった。
そんなところは、遺骨一体につき一ドルといった契約で、近くの部落に協力を求めた。
日時と引き取り場所を決め出向くと、袋にいっぱい遺骨を拾って届けてくれもした。
作業が進むにつれ、新しい情報提供者も次々と現れた。
しかし、残念ながら予定した以上の収集は続けられない。
合同慰霊祭の前に集めた骨を焼かなければならないし、荼毘の前に収集を打ち切らざるを得なかった。
残った遺骨や情報の処理は、収集団の世話をしてくれた三井金属鉱業ホンアラ駐在所と、ソロモン政庁によく頼み、いずれ船便などで送ってもらうように話をつけた。
快適なバンガロー 日曜には子供たちと交歓
タンベア暮らし
一日の作業を終え、身体を休めに帰る宿舎。
その居心地がいいか悪いかは、士気にも影響してくる。
ところが、タンベア・ビレッジがどんな施設なのか、日本をたつまでは旅行代理店に訪ねても、さっぱり要領を得なかった。
「なにしろ、あちら方面へお客さまを世話するのは初めてでして・・・」
「電気の無いバンガローだそうで」
「七十人くらいは収容可能ですから・・・」
と、全くたよりない。
おまけに、蚊取り線香と殺虫剤を持参のこと、と但し書きがついたものだから、団員たちは内心穏やかではなかった。
「ニッパハウス(ニッパ椰子の葉で造った家)にザコ寝だな」と覚悟を決めていた。
初めの連絡では、ホニアラのホテルが宿舎に当てられるという話だった。
島の中心でどこへ行動するにも便利と考えていた。
急に変更になった表向きの理由は「収容力が不足」とのこと。
しかし、本当のところ、首府の真中のホテルには外人観光客もくるし、薄汚い格好をして骨集めは困る----と政庁の配慮もあったらしい。
ホニアラから西へ四十キロ以上離れたタンベアは、日本的な表現を借りれば過疎地である。
恐る恐る着いてみたら、まぎれもなくニッパハウスが海岸に並んでいる。
だが、想像していたこととは大分違っていた。
外観はバンガローであっても、形式はレッキとしたリゾートホテルだったのである。
屋根はニッパヤシ、壁床は竹造り、それが十七棟と、他にダイングルーム、バーが別棟になっている。
バンガローは三人用と六人用で、それぞれベットと洗面所、西洋式トイレ、シャワーの設備がある。
電気の代わりにランプがついている。
部屋割りが済むと「これなら申し分ない」と団員の気分もすっかりほぐれた。
マネージング・ディレクター(支配人)の肩書きを持つのはターリングさん。
ストックホルム生まれのスウェーデン人。
「長いことソロモン政庁のもとでヤシ、ココアの栽培指導に当たっていたが、三年前にこのホテルを建て、経営を引き受けた」と言う。
どちらかといえばヤンキー気質の愉快なオジさんだ。
こんな辺ぴな場所にホテルを建てたのは辺地振興策で、部落の酋長の所有地を政庁で買あげ、それをホテル経営会社に貸し付け、助成金も出している。
部落民が株主。
ホテルのボーイも株主と聞かされてびっくり。
「気安く頼みごともできないぞ」と笑いあった。
ターリング支配人もボーイ達も、収集団の仕事を理解して気を配り、よく世話をしてくれる。
団員とボーイはすぐに仲良くなり、国際親善が繰り広げられた。
洗濯、飲み水運びなどの用事を頼むと、何でもやってくれた。
お礼にタオルや扇子やタバコをプレゼントすると大喜び。
しかし、こっちがやると言わなければ決してねだらなかったし、滞在期間中に物品が無くなったことは一度も無かった。
「英国式のしつけのよさが身に付いているのだろうか」と感心したほどである。
このタンベア生活は、まことに快適で、楽しいことも多かった。
バンガローの裏側には、椰子などの木立があり、すぐに砂浜が続いて、その先に青い入り江が広がっている。
仕事を終えると、団員たちは海水浴をしたり、部落民からカヌーを漕いでもらってサンゴ礁へ夜釣りに出かけた。
日なたは暑くとも、湿気が少ないせいか、木陰にはいると涼しい。
朝の起きがけや夕食前に、椰子の葉陰で休んでいると、海風がそよそよと吹き渡り、楽園そのものだった。
十一月からの雨季が近づいた前兆で、空模様がぐずつく日もある。
夕方になるとスコールが襲ってきた。
バケツの水をまくような、ものすごい雨足だ。
団員たちは奇声を上げながら、素っ裸で飛び出し、シャワー代わりにスコールを浴びた。
何より団員の気持をほぐし、よい想い出になったのは、原住民との交歓である。
日曜日に、セント・ジョセフ中級学校の生徒達がブラスバンドを演奏、近くの部落の初級学校の児童たちが踊りで慰問してくれた。
部落民と一緒に"メラネシア式"のパーティーを催した。
広場いっぱいに、椰子の葉を座席、バナナの葉をテーブル代わりに並べる。
魚や肉やタピオカイモを、バナナの葉で包んで焼いた料理を、ビールを飲みながら手づかみで食べる。郷土色豊かな晩餐だ。
夜になると、バンガローボーイたちを招き、ウィスキーを飲みながら語り合う。
英語の単語を並べ、身振り手振りで結構通じる。
「君のガールフレンドは美人か」
「日本へ行ってみたいな」
など話がはずんだ。
ギターでかき鳴らす島の歌、「ウェルカム・ソロモン」の調べは、「南の国にいるのだなあ」という実感を高まらせるものだった。
晴れた夜は、また見事な星空が広かった。
天の川が白く流れ、満天に星が輝く。
そしてガダルカナルを去る日、早朝の飛行機に乗るため午前二時半ころ起きると、南の空に十字星がまたたいていた。
山陰に低く隠れていたのが、夜半に高く昇ってきたのである。
多くの兵士たちが戦いのさなか、望郷の念にかられながら振り仰いだであろう十字星が・・・。
















