日本陸軍 第二師団 歩兵第十六連隊 新発田 あやめ会 戦記 戦死者名簿 ガダルカナル 雲南 ビルマ ジャワ ノモンハン 遺骨収集 政府派遣
暗黒の孤島に遺骨を求めて6
二ヶ所に慰霊柱 弔辞に団員たちも男泣き"
霊よ安らかに
「オーステン(アウステン)山の守兵は、腐木のように動かない。屍(し)体は足の踏み場もない。生きているものと、死んでいるものとそれから腐ったものと、白骨になったものが、枕を並べて寝たまま動かない」
(歩一二四連隊、小尾靖夫少尉の日記)
「夜が明けると、高地は屠殺場のような光景を見せていた。それ以来、ここは"血染めの丘"として記憶されるようになった。」
(ジョン・トーランド「ザ・ライジング・サン」)
「重患者は気の毒ながら骨となってガ島の壕内にとどまるほかはなかった。
杖にすがって、砂浜寄りの二十キロを歩く病兵の姿も哀れであった。自決の銃声を、椰子の葉陰に聞くのは一倍哀れであった」
(伊藤正徳「帝国陸軍の最後」)
「数千の将兵を、作戦失敗の犠牲として、この孤島にさらした。その直接の責任は自分にある。まさに自分の罪である」
(辻政信「ガダルカナル」)
ノートに書き留めてきた戦記の一説を、宿舎のランプの下で読み返す時、この島での戦いがどんなに凄まじかったか、今度の収骨がどんなに大きな意味をもつかを改めて痛感する。
こうして島を訪れなければ、二万一千の霊は永久に浮かばれなかっただろう。
生き残った戦友たちも、自責の念に悩み続けたことだろう。
実働一週間で、集めた遺骨は六千八百五十柱。
ばらばらになり、頭蓋骨もない遺体の数を正確に数える事は難しく、あくまで推計である。
少ない人手と、限られた日数で全遺骨を集める事は、とても出来るものではない。
海に流されたり、ジャングルに埋もれ、収集不可能な遺骨もある。
遺族だって、初めからそのことは承知している。
「ただ骨を拾いにきたのではない。みんなの霊を連れにきたのだよ」とささやきかけていたが、三分の一まで集め得たのは、努力のたまものと言えるだろう。
「きっと迎えに来るからな」と叫んだ約束。
それを果たした団員の表情から、ようやくきびしさが消えた。
「やっと肩の荷がおりた」---収集団派遣に奔走した県実行委員長の横山三義さん、事務局長の阿部茂さんらは、夜の語らいでしみじみと述壊する。
「いままで"感無量"という言葉を使ったことが何度かあるが、みんなウソに思える。こんなに感無量なことはない」と佐藤典夫班長。
県内の千四百四十一人の遺族から托された供物も、それぞれふさわしい場所に埋めた。
そのうち三分の二を一人で引き受けてきた佐藤明治さん(五一)=長岡市・美容院経営=は、「やっと責任が果たせました。晴れて遺族に報告が出来ます」と目をうるませていた。
集めた遺骨は、宿舎の近くの広場に積み上げて焼いた。
薄汚れていた骨が、焼けると真っ白になった。
白布の袋に入れ、一部は団員が持ち帰り、残りは船で送る段取りをつけた。
厚生省派遣団と協力団の話し合いで帰国したのち大部分は千鳥が渕霊園に納め、一部を新潟、福島、宮城の各県知事からの申請により分骨することに決まった。
合同慰霊祭の前日、このたびの収集を記念し、戦死者の冥福を祈る為に、慰霊柱を立てようと相談がまとまる。
さっそくホニアラの製材所で高さ三メートルほどのラワン材の柱を作ってもらい、十六連隊出身の僧侶、矢嶋聖阿さん=東京都=が墨汁で慰霊の言葉を記した。
建立の場所は、タンベア・ビレッジの海岸に一本、血染めの丘に一本である。
この丘は、ヘンダーソン飛行場の背後にある標高五十メートルほどの草山で、日本軍はムカデ高地と呼び、文字通り血みどろの戦いが行われた。
ローさんの案内で丘に登り、場所を選定してもらった。
ローさんは、英国在郷軍人会のホニアラ支部長で、政庁に勤め、島の戦跡保存に力を入れている人である。
最も奥まった"第一の丘"に決め、突貫工事に取り掛かる。
穴を掘り、石を積み上げ、木柱を差し込んで固める。
大勢の団員の中には、土建屋さんもいるからお手のものだった。
そこは記念柱を建てるのに、ふさわしい環境だった。
斜陽を浴びて丘の草原が輝き、間近に見上げるオーステン(アウステン)山のすそに、ルンガの流れが白く光っていた。
振り返ると、ヘンダーソン飛行場が一望のもと見おろせた。
「日本の遺骨収集団がこれを立てる一九七一十月国のために生命を失った日本とアメリカの兵士の記念のために」---慰霊柱の裏には、ローさんに頼んで英文でこう書き込んでもらった。
おそらく、この先ガ島を訪れる多くの人たちに激しかった戦いのむなしさと、兵士たちの友情の物語を伝えてくれるだろう。
十月二十三日、合同慰霊祭はタンベアの広場で、素晴らしい青空の下で営まれた。
海を背景に祭壇を設け、デービス主席弁務官をはじめ政庁の役人や、部落民も参列した。
「残念ながら、全部の遺骨を集めることは出来ませんでした。しかし、英霊のみなさん、私たちの胸に抱きつき、足にすがって、なつかしい日本へ帰ってください」
遺族代表の涙ながらの弔辞にたまりかね、団員たちも男泣きに泣いた。

宿舎に当てられたバンガロー形式のリゾートホテル。ボーイとは友達付き合いになった。

作業を終えた日の夕方、団員たちは”血染めの丘”に向かい、記念の慰霊柱を建てた。

"南海名物"の椰子は、原住民にとって大切な食べ物。島の経済を支える輸出品でもある。
ソロモン紀行 極限の飢え救う "餓島" 今や食べ物の宝庫
ヤシリンゴ
「ヤシリンゴ見つけたから、食べてみませんか」
休養に当てられた日曜日の昼下がり、海辺の木陰にトウイスを出してうとうとしていると、杉林清蔵さんに声をかけられた。
ヤシリンゴ?
聞かない果実の名だな、と首をかしげながら振り向くと、それは皮の色が茶褐色になった椰子の実から、緑色の芽が出たものだった。
なるほど、形がリンゴそっくりだ。
ナタで叩き割ると、果汁は乾いてしまって、殻の内側に牛乳をカンテンで固めたような果肉が分厚くついている。
ナイフで切り取って食べると、ふわふわした舌ざわりで青くさいパイナップルのような味がする。
正直言って、それほど美味いものではなかった。
「このガダルカナルで飢え、痩せ衰えたとき、こいつで助かったんですよ」
「そういえば、木の根であれ、トカゲであれ、食えるものは何でも食ったっけ」
「正月の特配が、手の平に乗るほどの米と、乾パンとコンペイトウ、それにタバコが一本」
吉井邦夫さん、佐藤元春さん、それに清水佐忠二さんと遺骨収集団が寄って来て、ひとつのヤシリンゴをめぐって、"餓島"の思い出話に花が咲いた。
ガダルカナルの戦いの記録によると、補給を絶たれた日本軍の窮乏は、想像を超えるものであった。
米軍陣地を占領して"ルーズベルト給食"にありつこうとしたが、負け戦ではとんだ思惑はずれ。
先に上陸した部隊が骨と皮ばかりになり、後続部隊の食糧を盗む泥棒集団も出現した。
事実、食べ物を巡る友軍同士の奪い合いもあったと聞く。
いたましいことである。
栄養失調になり、生と死の極限に置かれたときに、そうした行為があったとしても、なんで責めることができよう。
かっての兵士たちにとって、椰子は"思い出"そのものであった。
収骨中に喉がかわくと、原住民に頼んで、高い木の上から実を落としてもらった。
落とした実を全部持ち運ぼうとすると、「ちょっと待って、これは不味いからダメだ」と、原住民は黄色く変色し始めたものを捨てて、薄緑色のつやつやした"グリーン・ココナッツ"だけを選んだ。
殻に穴を開けて汁を飲むと、炭酸の抜けたサイダーみたいな味がして、けっこう美味かった。
椰子の実は島に住む人々にとっても、なくてはならない栄養補給源である。
黒人たちは、そのほか、タロイモ・タピオカ・サツマイモ・ヤムイモ・パナなどイモ類を常食としている。
最近は陸稲の栽培も始まり、黒人の中でも一部給料生活者は米を食べる習慣をつけている。
野菜や果実は、日本でとれるような品種が、この南の島でもいっぱいとれる。
茄子・南瓜・大根・トマト・ピーマン・インゲン豆・レタス。
そのほか、オーストラリアからジャガイモ・玉葱・キャベツ、日本から白菜・ホーレンソウ、それになんと"古々米"を輸入していると聞いてびっくりした。
バナナ・パパイア・パイナップル・マンゴー・ドリアン・・・。
果実にも事欠かない。
マーケットに山と積まれ、二十セントコイン(八十円)をひとつ差し出すと、大きなバナナの房が手に入った。
宿舎のタンベア・ビレッジでは、そうした野菜や果実に肉類を使って、スキヤキ、チキンカレー、魚スープ、茄子漬け、酢の物、と毎日手を変え品を変えての食事が出た。
「日本人には米が良かろう」と、わざわざオーストラリア米を用意してくれた。
しかも、全体の味付けがあまりにも日本的なので、支配人に訊ねると、やはり訳があった。
三井物産の子会社であるブリティッシュ・ソロモン貿易会社の社員でもう八年もこの島に駐在している渡辺さんという人がいる。
その家で働く黒人のメードのジョイさんが、奥さんの指導で、日本の味付けをすっかり
覚えた。
収集団の滞在中、このジョイさんが宿舎に泊まりこみで"専属まかない婦"をやってくれた。
オーストラリア米以上に、予期しない味覚も楽しめた。
それはカツオである。
ソロモン政庁との契約で、大洋漁業がこの海域でカツオの試験漁獲をやっている。
船腹が満パイになると、日本へ帰る前にホニアラ港へはいってくる。
静岡県沼津市の第一静浦丸、神奈川県三浦市の南海丸、海竜丸といった、七〜八百トン級の漁船がときおり姿を見せる。
情報がはいるたび、さっそく車に乗ってお出迎えだ。
指で押すとハネ返ってくるような、身のしまった四十センチほどのソロモン産カツオ。
そいつを十匹、二十匹と頂戴し、刺身や味噌煮にしてたらふく食べた。
帰国してから「島では何を食ったね」と、半ば同情するような口調でよく質問されたが、このように食べ物には不自由しなかったのである。
「やせる覚悟できたが、反対にふとってしまう」
「日本にいるよりいいな」
「戦争の時、こんなに食えればなあ」
と食卓での会話もはずんだ。
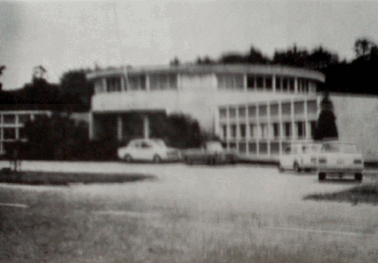
首府ホニアラに建つ国会議事堂。島々から選出された黒人議員が、英国人の指導で立法にあたっている。
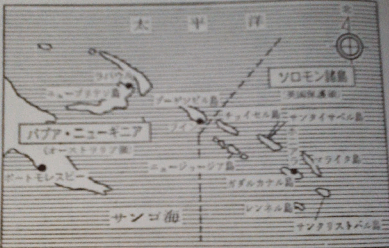
着々と経済開発 国会に17人の黒人議員
独立をめざして
英国保護領ソロモン諸島というのは、東西一千キロにわたって、二列に並ぶ島々の総称である。
チョイセル、ニュージョージア、サンタイサベル、マライタ、ガダルカナル、サンクリストバルの六つの主要な島のほか、無数の小島とサンゴ礁から成る。
太平洋戦争の後、これらの地域を再び統治することになった英国は、島々の中でも最も広い平野を持つガダルカナルに目をつけ、政庁を置いた。
島を結ぶ交通機関は、船と飛行機である。
現在、太平洋一帯の英国領を統轄するサーマイケル・ガスという高等弁務官が着任している。
その下に、ソロモンの政治を担当するデービス主席弁務官、スミス財務長官、ジョーンズ総務長官のトリオがいる。
政庁に誇らしげにひるがえるユニオンジャック。
島では多数の現地語と、英語と混成したピジンイングリッシュが使われているが、公式の言葉はもちろん英語である。
首府ホニアラの町は、緑の木々と芝生の中に白い家々が遠慮がちに建っているような印
象を受ける。
街路樹は、赤い花のトンネルをつくるクリスマスツリー、生垣に深紅のハイビスカスが咲きこぼれる。
庭には甘い香りをまき散らすフレンチパニーの白い花。
静かな住宅地に足を踏み入れると、そこは花園。
公害の国から来た旅人には、羨ましい町である。
このホニアラには、戦争のあと米軍が残した施設をもとに発展した。
ソロモン諸島を発見した探検家の名前を付けた、メーンストリートの「メンダナ通り」が真中を貫き、通りに面してソロモン政庁、弁務官事務所、国会議事堂、中央警察署、郵便局、銀行などが並ぶ。
ホテルや商店も軒を連ねている。
マタニカウ川に沿って中国人街ができ、そこには"味は太平洋一"と名高い中国料理の「ランタン・レストラン」もある。
町の中央部に突き出たクルツ岬は天然の良港で、波止場には輸出用のコプラの倉庫が並ぶ。
火力発電による電気、上水道も完備している。
映画館も一軒あり、私たちが滞在している間、アメリカの映画を上映していた。
"未開の島"のイメージは、消さなければならない。
三十年前の時点で針を止め、偏見にとらわれていたことがはずかしくなった。
日本が廃墟から立ち直り、経済成長を遂げている間に、南の島だって変わらないはずがないのである。
しかし、一週間、十日・・・と島のあちこちを歩き回ってみると、ホニアラの町の美しさは、黒人とは調和しない、なにか異質のものに思えてきた。
白い家も、広いアスファルト道路も、まぎれもなく白人の造ったものである。
丘の上や海岸に建つ、住み心地の良さそうな家は白人の所有。
入り江に浮かぶヨットもそうだ。
ホテルやレストランは白人の出入りする場所で、黒人は役人とかよほどのエリートでなければ仲間に入れない。
そして政治は英国人、経済はオーストラリア人と中国人(華商)に握られているのが、島の実態といえよう。
広大な椰子のプランテーション(農園)は、ほとんどが白人の所有である。
かって原住民の土地が、ボタンやウィスキーの空き瓶と交換で白人の手に移っていった話を聞いた。
そうした無知につけ込む様な取引を防ぎ原住民の所有権を保護するため政庁では「不在地主を認めず」などの土地政策をとった。
文明開化の道を歩む---とはいっても、町をはずれれば、まだ昔ながらの生活様式が見られる。
町に住む一部の給料生活者を除くと、ほとんどの原住民はニッパハウスでランプをともし裸足で暮らしている。
世界保健機構の援助によるマラリア撲滅事業が進み、患者は希にしか発生しなくなった。
しかし、第二の風土病といわれる結核、それに皮膚病がはびこっている。
衛生思想の向上が残された大きな仕事でもある。
英国は、このソロモン諸島を近い将来に独立をさせたいと開発計画を立て、投資を続けている。
まず島民の教育に力を入れ、教会が成長の資金を受けて、初級四年、中級三年制のミッションスクールを運営している。
教員養成学校や海外留学制度も設けている。
まだ、義務教育ではないが、そうした教育を受けた原住民が、すでに警察官、政庁事務官、教師といった職業につき、病院ではインターン生が熱心に学んでいた。
英国の統治下にあるとはいえ、三権分立を憲法の基本とし、黒人が各部門に登用されている。
国会には、選挙で選ばれた十七人の黒人議員が、弁務官の任命による五人の英国人議員とポストを分け合っている。
島の経済をささえる主要産物はコプラである。
椰子の脂を削り取り、せっけんなどの原料にする。
ほかに木材、貝殻、ココア、わずかな金などを英国、オーストラリア、日本などへ輸出している。
これだけでは不足なので、地下資源の開発に力を入れ始めた。
アメリカ、日本、オーストラリア、などの協力で合弁会社を設立し、ニッケル、銅、ボーキサイトの採掘に乗り出している。
英国の保護から離れ、国際社会への仲間入りをめざすソロモン。
その経済的基盤はようやく固まりつつあるが、自治確立のための人材がまだ不足している点に、悩みがあるように見受けられた。
人なつっこくて陽気 踊りがなにより楽しみ
黒い膚の人々
モーリス、十七歳。
タンベア・ビレッジのボーイ。
赤いラプラプ(腰巻)を巻いて、さっそうと歩く。
セント・ジョセフ・スクールを卒業して、すぐホテルに勤めた。
ペンダントを胸に下げ、部落きってのモダン青年。
気がいいものだから、みんなにかわいがられ、声がかかる。
「トーキョー、オーサカ、コーベみな知っている。行ってみたい」という。
ジョージ二十五歳。
同じくボーイ長。
ごつい顔に似合わず、誠実な人柄。
オーストラリアへ留学して、ホテル業務を勉強してきた。
「まだ嫁さんがいない」とはにかむが、将来は経営のスタッフになるのだろう。
ベルナード、八十歳。
英語はかなりしゃべれるが、字は書けない。
カミンボの日本軍撤退のもようなどを、よく覚えている。
ニッパハウス造りの名人?で、「タンベアのバンガローは俺の作」と自慢する。
短命なはずの原住民にしては、信じられないような寿命で、わが近ドクターによれば「自分の歳を忘れたのだろう」。
ジョン三十歳。
マイクロバスの運転手。
女房と二人の子連れ、「ホニアラには、なにかいいことがありそうだ」と、他の島からやってきた。
派手なアロハを着て、裸足で巧みにアクセルを踏む。
指示されるままに、朝から晩まで黙々と運転し、骨集めの手伝いまでしてくれた。
「別れがかなしい」と涙ぐんでいた。
そのほかギターをかかえて道案内を勤め、パパイアの皮をむいてくれたボログスターの青年、アロンベティとウィリス。
みんなひとなつっこく、陽気なメラネシアの人たちだ。
"メラネシア"というのは、南太平洋の中でもソロモン、ビスマーク、ニューヘブディース諸島などの地域を指す。
グァム、サイパンなどのミクロネシア、タヒチ、トンガなどのポリネシアとは区別される。
その昔、アジア大陸から海を渡り、移動してきた同じ民族といわれるが、現在ではメラネシア、ミクロネシア、ポリネシアそれぞれに風俗習慣、皮膚の色や形が多少異なっている。
"黒い島々"を意味するメラネシアが、住民の膚の色が最も黒い。
ソロモン諸島のメラネシア人は、総人口約十七万のうち九〇%以上を占めている。
そのほかポリネシア人、白人、中国人などが住む。
遺骨収集に訪れたガダルカナルの人口は約三万、そのうち首府ホニアラは約一万三千で、人口集中が進んでいるようである。
メラネシア人の体格は、ちょうど日本人くらい。
男は割合ハンサムがいるのだが、どうも女に美人がいない。
画家ゴーガンがほれ込んだタヒチの女と比べて「同じ南太平洋なのにどうしてこんなに違うか」といささかガッカリ。
島の住民には失礼な話だが、美的感覚の差は仕方が無い。
スカートにブラウスかワンピースを着ていて、期待した上半身裸の習慣は、よほどの老人か幼児でなければみられなかった。
結婚適齢期は男二十一歳、女十四歳だという。
「奥さんは何人もてるか」とベルナード老人にたずねると「とんでもない。キリスト教
のおきてで男一人に女一人だ。もっとも相手が死ねば再婚できるがね」とウィンクをしてみせた。
原住民の仕事は、役人、商社の下働き、運転手、椰子園の作業員を除けば、大部分が農耕である。
農業という大げさなものではない。
年中暖かいこの土地では、家具も衣類もあまり必要としないし、自分の食い扶持と多少の換金作物を育てていればコト足りる。
日本の労働者あたりに分類させると、さしずめ"潜在的失業者"になるのだろうか、完全雇用であくせく働くより、こっちの方がよいように思えてくる。
そして、島でのなによりの楽しみは、踊りと歌である。
リズムが聞こえてくると、女も子供も調子を合わせて踊り出す。
谷奥のニッパハウスからも、若者のひくギターのメロディが流れてくる。
サッカー、ラグビーといった英国式スポーツも盛んで、土・日曜日になると学校のグランドでプレーする黒人たちの姿が見られた。
原住民が、私たち日本人に寄せる好感。
手前みそな話でなく、それをいろいろに機会に意識した。
どういう理由なのか、よくわからない。
歴史的に見て、支配民族である白人とは、超えがたい壁がある。
それに比べて、同じ太平洋の民族で、膚の色も近い日本人のほうが親しみやすいのだろうか。
ソロモンが独立したとき、日本と友好関係を結び、協力を望みたい---という雰囲気が指導層にあるのは事実である。
そのへんの感触を詳しく知りたいと思い、国会議長で資源開発委員長を兼ねるカウシマイ氏に会見を申し込んだ。
同氏は、"将来の大統領候補"といわれ、資源開発のため今年四月に日本を訪れたこともある。
しかし、ちょうど出身地のマライタ島へ帰っていて、話を聞けなかったのは残念なことである。
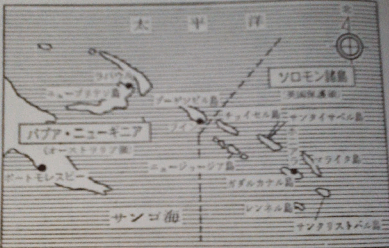
メラネシアの人々。裸で、呑気に暮らせる南の島の住民は、現代の幸せ者なんだろうか。
あふれる国産品 自戒しないと"侵略"の汚名
島の中の日本
南の島にも、数は少ないけれど日本人がいる。
私たちが訪れたとき、ガダルカナルには"七人の侍"が頑張っていた。
資源開発の三井金属鉱業、木材やコプラの取引をする安宅産業、カツオ漁の大洋漁業、それに三井物産の子会社である太平洋水産とブリティッシュ・ソロモン貿易会社の社員たちである。
ソロモン諸島全域では、ほかに十人。
レンネル島のボーキサイト採掘場に三井金属鉱業の技術者、ニュージョージア島にブリティッシュ・ソロモン貿易の駐在員、ショートランド島に日商岩井の商社マン。
長い人は、もう滞在八年にもなり、平均して二、三年というところらしいが、南の島での勤めは一見のんびりしているようでも「いかに黒人の信用を得るか」など気遣いが大変だという。
原住民を雇用するにも、取引するにも、相手が素朴で、いったん思い込んだらなかなか考えを変えようとしないだけに、手綱さばきの妙が要求される。
駐在員たちは、こんな話をしてくれた。
ソロモン政庁との契約操業で、カツオを満載した大洋漁業の船が入港する。
船を視察にきた黒人事務官が「どっさりとると、ソロモンのカツオがいなくなる」と心配したという。
期せず、世界の海を荒らし回る"日本式漁業"を皮肉られたようなものだが、そのへんの
事情説明に一苦労する。
鉱山の作業や海の荷役に原住民を使うとき、「黒人はのんびりしているから」と適当に仕事をやらせ、笑顔をやたら振りまいていたのでは失敗する。
よく働く者も怠け者もいるので、放任すると「働いても給料が一緒では・・・」と不満やサボリ気が広がる。
「長く付き合う場合には、ビシッと言うべきことは言わないとナメられますね」と、現場監督の黒人使いのコツを語る。
このたびの遺骨収集は、これらの日本商社のうち、特に三井金属鉱業のお世話になった。
それには、次のようないきさつがあったのである。
我が国は、年間百万トンのアルミニウムを生産しているが、原料のボーキサイトはすべてオーストラリアあたりからの輸入。
アルミ需要は、今後ますます伸びることが予測されるため、ボーキサイトの自主開発が政府や業界の望みであった。
ちょうど資源開発をめざすソロモン政庁が、銅、ニッケル、ボーキサイトの国際入札を行い、三井金属鉱業がレンネル島の権利を手に入れ、一昨年九月にガダルカナルのホニアラ駐在所を開設した。
埋蔵量三千万トンが見込まれ、開発資金六十億円を投じて、昭和五十年には積み出し第一船を予定している。
同社の尾本信平社長が今年(昭和46)三月、外務省派遣オーストラリア経済調査団の副団長として現地を訪れたとき、まだ遺骨が散乱している話を聞いた。
「こんな状態では、とても開発事業は進められない」と外務、厚生両者に強く働きかけた。
それが戦友。遺族の運動とうまく合致して、急速にガダルカナル遺骨収集派遣が実現し
たのである。
同社は、神岡鉱業所の"イタイイタイ病"のレッテルを張られたときだけに、イメージチ
ェンジの狙いもあったのだろう。
それはともかく、上田俊郎、尾本衛の両駐在員の協力ぶりは、仕事そっちのけでまさに
献身的だった。
日本人は、指折り数えるほどしかいないのに、この南の島での"メードイン・ジャパン"の氾濫はどうしたことだろう。
特に自動車、電気器具、時計などは七〇%から八〇%が日本製である。
東南アジア方面への進出は知っていたが、南太平洋の島々までとは、以外を通り越して
あっけにとられた。
ソニー、サンヨーなどとローマ字で書かれた袋をぶらさげて歩く黒人。
すまし顔で日本製の自動車を乗り回す白人。
日本語の通じないホニアラの町角で、ぼんやり眺めていると、暑さで頭がおかしくなっ
たのではないかと疑いたくもなる。
私たちが使ったマイクロバス、タクシー、レンタカーは、ほとんどダットサン、トヨタ、いすゞ・・・。
黒人のアベックがホンダのオートバイにまたがって、手を振ってゆく。
客待ちの運転手に「君のタクシーは日本製だな」と声を掛けたら「おー、ナンバーワン
」ときた。

日本製の自動車が、わがもの顔に並ぶ風景、ホニアラでも、お隣のラバウル、ポートモレスビーでも見られた。
マーケットで日本製の缶詰を買っていると、黒人が寄ってきて時計を見せろという。
しばらくいじり回して「セイコーはナンバーワン」と、欲しそうな顔をする。
"ナンバーワン"は"ベリーグッド"の意味らしいが、とにかく日本の評価は高い。
ところが、それを売ったり修理したりする代理店の多くは中国人(華商)なのである。
この取り合わせ、なんとも奇妙な現実だ。
よその国から資源を求め、加工して、またよその国へ売る"貿易立国"日本。
評価の高いうちはいいが、身勝手な経済成長がエスカレートしたとき、善良な黒人から経済侵略の烙印を押されることになりかねない。
自戒すべきことである。

ガダルカナルにある米軍機の残骸、南太平洋の島々には、こうした戦いの遺物がまだいくらでもある。
陽光さす"避寒地" 巡拝者の訪れを待つ激戦地
戦跡を巡り
世界中が観光地化するなかで、暗黒地帯といわれたソロモンの島々にも、ようやく陽光がさし始めた。
まずオーストラリアの人々の避寒地として、ホテルや遊びの施設が出来てきた。
戦いの跡を懐かしむアメリカの旧軍人や、物好きなヨーロッパのツーリストも訪れている。
タンベア・ビレッジのサイン帳をめくってみると、イギリス、フランス、ドイツなどの国籍が記されていた。
紺碧の海に浮かぶ緑の島とサンゴ礁の魅力もさることながら、島の各所に残る戦跡も観光資源になっている。
ガダルカナルの表玄関、ホニアラ空港の広場に、高射砲が空を睨んでいる。
「昭和十六年 大阪工兵廠」の銘がある。
ホニアラ近くの部落に、不時着した米軍機がそのまま残骸をさらしている。
タサファロングやエスペランス岬には、輸送船や上陸用舟艇、魚雷などが赤錆びたまま波に洗われている。
激戦地のオーステン山(アウステン山)一帯は、今ではクイーン・エリザベス国立公園の名で呼ばれ、頂上近くまで自動車の登れる道がついている。
血染めの丘は絶好の展望台で、訪れる人も多い。
めぼしい戦闘のあった場所は、英国在郷軍人会ホニアラ支部の手で標識が立てられている。
タクシーに頼むと、これらの戦跡巡りをやってくれる。
ソロモンの島々では、ガダルカナルだけでなく、ツラギ、ショートランドなどの島、隣のオーストラリア領パプア・ニューギニアのブーゲンビル、ニューブリテンといった島々にも船の残骸やトーチカ、大砲などがゴロゴロしている。
それに連合軍がつくったメモリアル・フィールド(記念碑または墓地)が花に飾られ、ひっそりと巡拝者の訪れを待っている。
これらの戦跡に、さる昭和三十年、日本の遺骨収集団が建てた慰霊碑も加えられた。
この年の一月から三月かけて、厚生省の「南方方面濠地域遺骨収集団」が運輸省の練習船「大成丸」で、ソロモン、ビスマーク、東部ニューギニア、アドミラルティ諸島などを巡回した。
そして、ブーゲンビル島ブイン(陸軍呼称エレベンタ)、ニューブリテン島アイタベ海岸など八ヶ所ら石碑を建立した。
島々に散らばるいろいろな戦跡の中で、最も関心を持ったのは山本五十六連合艦隊司令長官の戦死の地であった。
山本長官は、いわずと知れた本県長岡市の出身。
太平洋戦争突入には、最後まで反対したが、平和への意図むなしく会戦となるや、勇猛果敢に米軍を震え上がらせた。
しかも、敵味方を問わず最も敬愛された提督である。
昭和十八年四月十八日の早朝、ラバウル基地を飛び立った山本長官の一式陸上攻撃機は、宇垣参謀長の僚機を従え、ゼロ戦六機に守られて南東約三百キロのブーゲンビル島へ向かった。
第一線将兵の激励が目的であったが、それは日本海軍にとってかけがいのない人を失う運命の日となった。
同島南端のブイン上空で、米軍のP38戦闘機十八機の迎撃を受け、長官機は黒煙を引いてジャングルに墜落した。
正確にいうと、ブインの日本軍基地から林道を二十キロ、アクという部落からワマイ川沿いにジャングルを約五キロ下った地点である。
記者はこの郷土の偉人の終焉の地に、是非行ってみたいと考えていた。
ガダルカナルのから北西へ約七百キロ、ブーゲンビルの中心キエタへ飛び、そこで乗換えてさらにブインへ飛び、二泊する日程を組んでおいた。
しかし、結局はこの計画は中止せざるを得なかった。
理由は、天候が心配だった。
十一月からの雨季を控えて空模様がぐずつきはじめ「雨が降ると、ブインへ行くローカル空路があてにならない」と航空代理店におどかされ、いささか心細くなったのである。
なにしろ、この地域の空路は、週に一便か二便しかない。
「欠航になった場合、団体なら臨時便をチャーターする手もあるが、単独行動だとあとのスケジュールがみんなくずれますよ。一週間くらいの余裕をみないことには・・・」と、日本流の"綱渡りスケジュール"を戒められた。
断念したもうひとつの理由は、ガダルカナルからニューブリテンへの戦跡巡拝に来ていた元南東方面艦隊司令長官の草鹿任一さんに会えたことである。
山本長官の墜落地点へは、小説「山本五十六」を書いた作家阿川弘之さんが四十一年に訪れているが、このあと四十六年に草鹿さんもはいった。
戦時中、日本軍の「桃太郎農園」で働いていた酋長ボーバケの案内で、八十過ぎの老体を黒人の担架にゆだね、ジャングルに分け入った話を聞いた。
「山本さんは偉い人でしたよ。私は死ぬ前に、是非山本さんの亡くなられた場所でお祈りしたいと念願していたのです。機体は、エンジンと胴体と尾翼の部分が切り離された形で、いまでもそのままジャングルに埋もれ、こけがはえて・・・。その部分品を持ち帰り、一つは千鳥が渕に納め、もうひとつは長岡市に寄贈しましたよ。」
「日本だったら、さしずめ観光地になっているでしょうね」と合いヅチを打つと、草鹿さんは眉を曇らせてつぶやいた。
「観光だなんて、そりゃ困りますよ。山本さんの心境を考えると、あの場所を見てもらいたくない。なんとかして、飛行機の残骸を土の中に埋めてしまいたいですね。」
パプア・ニューギニアの首府ポートモレスビーの書店で、最近発行されたこの国の案内書を手に取ってみたら、ジャングルの中の山本長官機がカラー写真で掲載されていた。

中央高地の砲台跡から望む母山(左)、妹山を望む母山の下、湾の奥にラバウルの街がある。
今も残る"日本" 印象的な緑、明るい町なみ
さらばラバウル
♪さらばラバウルよ
またくるまでは しばし別れの涙がにじむ
恋しなつかしあの島見れば 椰子の葉陰に十字星
この歌のおかげで、戦争を知らない世代でも"ラバウル"の地名は知っている。
ガダルカナルへ出発する準備に追われている時「是非ラバウルにも寄ってきてくださいよ。いいところです。どんなに変わったことか・・・。話を聞かせてください。」
と大勢の"ラバウル帰り"から頼まれた。
なんとなく郷愁を感じさせるような、その地名の響き。
歌にまでなり、もう一度行ってみたいと懐かしがられるラバウルとは、そんなによいところなのだろうか。
昭和十七年一月な、日本軍が占領してから終戦まで、ざっと三年半にわたって手中にあった。
ガダルカナルの勝利で勢いづいたアメリカ軍は、要塞化したラバウルを孤立させたまま、一挙にマリアナ、フィリピン、沖縄へと北上作戦をとった。
連日のように空襲はあったけれども、ここでは悲惨な戦いは最期まで行われなかったのである。
終戦後に、ラバウルから引き揚げた将兵は、約八万二千人と記録されている。
「ラバウル小唄」の明るいメロディーは、そこから生まれたのだろう。
ガダルカナルのホニアラから、ニューギニアのポートモレスビーへ戻り、遺骨収集団の人たちと分かれたあと、ニューブリテン島の北端、南緯四度にあるラバウルへ向かう。
プロペラ機で、ちょうど二時間の距離だ。
南太平洋の十字路といわれるこの港町は、なるほど風光明媚の言葉がぴったりの美しいところであった。
日本軍が、母山、姉山、花吹山などと名づけた火山群に囲まれ、深く、波静かなシンプソン湾がきらきらと光っていた。
湾内に浮かぶ松島、中島。
その奥まったところには、こじんまりとラバウルの町があった。
日本軍が作った、東、西、南の三飛行場のうち、町に最も近い東飛行場が現在のラバウル空港になっていて、あとの二つは使われていない。
空港に降り立つと、北海道の昭和新山に似た花吹山の赤茶けた山膚と、母山のみずみずしい緑が印象的だった。
日本製のタクシーで、湾に臨むコスモポリタン・ホテルに案内してもらう。
オーストラリア人の経営で、平屋建てのモテル形式の宿である。
モテルといっても、日本のいかがわしい施設と違い、いかにも南国風の清潔なもの、部屋にはシャワー、日本製のクーラーと電気冷蔵庫があり、一泊十ドル(四千円)、朝食二ドル(八百円)とまず申し分ない。
ラバウルには、日本人の商社員と家族ら十一人がいるという話で、そのうち毛利セキ子さん(二六)と空港で知り合った。
セキ子さんは東京都の出身で、日本へ自動車の整備を実習にきていた中国人と結婚し、この町に住んでもう四年、二人の子供が居る。
「寂しくなくなりましたが、やはり日本からいらっしゃる方は懐かしくて・・・」と家に案内し、オーストラリア製の"南太平洋ビール"をごちそうしてくれた。
翌朝、起きがけに黒人のマーケットへ行ってみた。
小学校のグランドほどの広場に、簡単なニッパ屋根の売り場を建て、果実や野菜、それに観光客目当ての貝殻細工や木彫りを売っている。
「アナタ日本ノ方デスネ。ワタシ、日本語知ッテイル。東京カラキタカ。船デカ。飛行機デカ」
いきなり話しかけられ、ビックリして振り向くと、変な黒人がニヤニヤしている。
もう一人の連れが「コノ市場ナンデモアルヨ。バナナ買ワナイカ」。
日本軍が長く占領していたので、五十歳前後の黒人は日本語を喋れるわけだ。
タバコを差し出しながら「日本の歌を覚えているか」というと「見ヨ東海ノ空アケテ、旭日高ク輝ケバ」「夕陽ケ小焼ケデ日ガ暮レテ」「桃太郎サン、桃太郎サン」と、立て続けにやり始めたのには二度びっくり。
セキ子さん親子の案内で、ラバウル見物に出かけた。
蒸し暑いのでクーラーをつけっぱなしで走る。
まず、花吹山の麓にある「戦没日本人の碑」に参拝してから官邸山に登った。
ここは戦前のドイツ統治時代に総監官邸があったところで、山本五十六長官もこの丘の
コテージに滞在したという。
緑の中に白壁の家が点在するラバウルの街並みと、入り江の眺めが素晴らしい。
湾に沿った快適なドライブコースを、街の対岸へ約十キロ、中央高地の砲台跡に登ると、日本製の大砲、機関砲、地下壕が残っている。
山を下って、さらに二十キロほど海岸を走ると、郷土部隊のガダルカナルへの出発地点、また撤退地点にもなったココボのトーチカ、船のスクラップなどが潮風にさらされていた。
近くのビタパカなは、花壇にいろどられたオーストラリア軍兵士の立派な墓地。
勝者と敗者の差を見せられた感じである。
湾に面した崖っぷちに、日本軍が防空用に掘った大きな洞穴が幾つかあった。
その一つ、水辺から二百メートルほども離れた穴に上陸用舟艇が五隻格納されていた。
竹の皮を敷いて、エッサエッサと引っ張り込んだという話だ。
入り口に黒人の木戸番がいて、一人二十セント(八十円)の見物料をとっていた。
たった二泊三日の滞在ではあったが、あちこち回ってみると"ラバウル帰り"の心境がわかるような気がした。
なんとなく去り難い情緒---それは、いまもなお残る日本人の足跡と体臭だろうか。
山と水が青い空の下で調和した、明るい南の町のたたずまいだろう。(おわり)
新潟日報社 山田 一介 記者
全国的に反響を呼んだBSN新潟放送の、鷲頭典彰カメラマンの活躍
今回の「ガ島」遺骨収集に際し、BSN新潟放送では収骨の実情を一般に報道する為に鷲頭典彰報道記者を同行させて取材にあたらせた。
鷲頭カメラマンは派遣団員に協力して縦横無尽に駆け廻り、収骨状況、民情、政治経済などあらゆる角度から現地の模様を取材した。
帰還の翌日実施された収骨報告慰霊祭当日は、県護国神社会場で、応急編集ながら迫力のある収骨の実況を映写して多数遺族の涙をさそい、その後現地での録音を取り入れて編集した記録映画「ああガダルカナル」を十一月五日夜全国放送、十一月十六日には、三十分番組として流し、更に十二月十八日及び二十五日の二回に亘り総合的見地で纏めたものを「カメラをかついで」の番組に放送し、各方面から多大な反響を呼んで感謝されている。
これらの記録フィルムは既に県下十数か所の遺族会等の席上に貸し出され、一般の観覧に供しているが、他県よりの希望も舞い込んで来るなど全国的に反響を呼んでおり、国際平和という問題に対する考え方や、戦後処理に対する政府のやり方について鞭撻する好材料とも受け取られている。
読んで好評を得た新潟日報社山田一介記者の連載記事と共に、眼で見て直に迫力を感ずる記録映画の一般に与えた感動は誠に大きく、各方面より絶賛の声が起こっている。
両報道員の労をねぎらいたい。
あとがき
ソロモン諸島のガダルカナル島。
第二次世界大戦史上重要な意義を持ったこの島は、旧第二師団に所属した吾々にとっては永遠に忘れることのできない痛恨の島である。
ここには、新潟、宮城、福島三県出身の将兵八千名を含む二万一千余名の霊が、だれ一人弔う者もいない密林の中で長い間放置されていた。
吾々自身の手で英霊の遺骨を故郷へ迎えたいと云うことは関係者の共通した悲願であった。
政府の収骨計画発表以来、これに協力すべく僅か三ヶ月の短期間に諸準備を整えるということは誠に困難な事業であったが、関係者の努力と県民各層の御支援によって実現出来たことと、派遣団員が一致協力し予期以上の成果を挙げて県民の期待に添うことが出来たことはこの上ない喜びである。
御後援戴いた県、市町村、各種団体始め御遺族関係者、一般県民、旧部隊関係者各位に心から感謝申し上げると共に、率先して報道員を派遣して協力戴いた新潟日報社、BSN新潟放送並びに現地でお世話になった、三井金属鉱業ホニアラ駐在員の上田俊郎、尾本衛両氏、太陽漁業 漢那武二氏、TAA航空のホワイト・ゆき子さん、三井航空サービス中野喜作の皆さんに衷心より謝意を表して擱筆する。
尚本書に掲載した写真は欠く団員及び一部新潟日報社より提供願ったものであり『南十字星の下に』と題する山田一介記者の十三回に亘る記事は、特に新潟日報社のお許しを得て転載したものである。
昭和四十六年十二月二十五日 事務局長 阿部 茂
昭和四十六年十二月三十日発行 (非売品)
編集者 長谷川 榮作 阿部 茂
発行者 ガダルカナル島遺骨収集団派遣 新潟県実行委員会
















